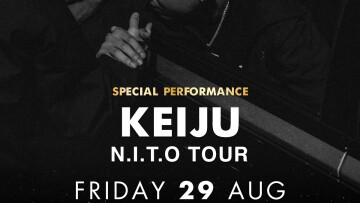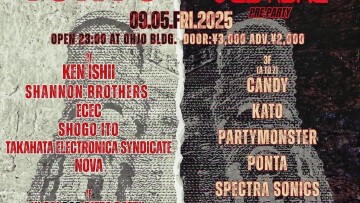1864年10月31日、ネバダ州はアメリカ南北戦争の廃墟の中から誕生した。ネバダ準州の州昇格によって、エイブラハム・リンカーン大統領の再選と合衆国憲法修正第13条(※奴隷制の廃止)の批准が確実なものとなり、究極的には合衆国の将来が約束されたのである。誇らしいと同時に痛みを伴ったネバダ州の歴史は、現在、州旗の左上に紋章として刻まれている2つの単語によって祀られている。その2語とはつまり、『Battle Born』(=戦いが生んだ[州])だ。
そのフレーズは、ブランドン・フラワーズの心の中に、これまで常に響き続けてきた。それはザ・キラーズがラスヴェガスにある自身のスタジオに付けた名前であり、また昨年5月、2008年の『デイ&エイジ』に続く新作に着手しようとバンドが再集結した際、まず曲名として挙がり、その後はテーマ的な試金石となって、遂にはアルバムそのもののタイトルとなるに至った言い回しである。しかし"戦い"には、必ずしも暴力と流血沙汰が伴うわけではない。メンバー4人のうち3人がソロ活動を行った1年の休止期間を経て、タイミングや状況というものが自分達の手強い敵になり得るということを、彼らはすぐに悟ったのだった。今回のアルバムが『Battle Born』というタイトルになったのは、当然の帰結だったと言って差し支えない。
「今まで僕が作ってきた、どの作品よりも大変だったよ」とブランドンは語る。「ザ・キラーズのこれまでの作品の中でレコーディングに最も長い時間のかかったアルバムだし、歌詞作りにも僕は一番長い時間をかけた。曲数は充分に用意してあると自分達では考えていたんだけど、その後、まだ足りないってことに気づいてね。それから『これで準備は万端だ』ともう一度確信できるようになるまで、ひたすら書きまくり弾きまくらなきゃならなかったんだ」。
それには時間を要したが、ザ・キラーズはそこに至るまでに既に多くの時間を費やしていた。結成以来10年間、その大半をツアーに明け暮れながら過ごしてきた彼ら。2010年2月、1年半に及ぶマンモス規模の世界ツアーのゴールがいよいよ目の前に迫ってきた時、バンドは岐路に立たされた。『ホット・ファス』『サムズ・タウン』『デイ&エイジ』のアルバム3作を合計1,500万枚以上売り上げ、地球の隅々までを訪れて、いつの間にか世界最大級のロック・バンドとなっていたザ・キラーズだったが、ブランドン曰く、「あらゆることを正しい観点から見直し、気持ちをきちんと整理する」時間が、自分達には必要だということに気づいたという。「マークとデイヴが、それを強く求めていたんだよね。一方、ロニーと僕は、他の2人も望んでいたなら、多分すぐに新作に取り掛かっていたんじゃないかな。だけどもしバンド内に1人でも『休みを取りたい』と思うメンバーがいたなら、そうするのが正しい選択なんだよ。だからああいった形でオフを取ったのは、間違いなく正しい手立てだったんだ」。
ブランドン、マーク、そしてロニーの3人が、それぞれソロ活動に手を出して成功を収めた後、昨年4月、チリで初開催されたロラパルーザ・フェスでヘッドライナーを飾ったザ・キラーズ。オーディエンスを熱狂させたその復活ライヴで、ロニーの言葉を借りれば、彼らは「また同じ部屋にみんなで集まって、曲を書きたい」と確信したのだった。数日後、彼らがまとめ上げた曲が、結果として本作『Battle Born』のリード・シングルとなった、「Runaways」だ。
壮大なスケールで描かれた小さな田舎町のドラマ「Runaways」には、ザ・キラーズの復活シングルとして人々が期待する全てが詰まっている。サイクロンのようなザ・フー調のギターや、モハベ砂漠の端から端まで轟き渡るほどの壮大なコーラスを伴って、彼らの帰還を告げる「Runaways」。この曲では、紛れもなくアメリカ的な表現で、ロマンスと楽観主義とが描き出されている。
本作収録曲中、最も初期段階に書かれた部類の1つで、アルバムの骨子となった同曲は、2009年の『デイ&エイジ』ツアー中に書かれたものだが、ブランドンによると、「この曲をどう扱ったらいいのか、僕らには分からなかったんだ。『デイ&エイジ』で、ザ・キラーズはポップ・グループ寄りになろうとしていたんだけど、「Runaways」はルーツ風でアメリカ的だったから。それで戸惑ってしまって。パワフルな曲だってことは僕にも分かってたけどね。そしてアルバムを作る段階になった時、僕ら4人の間には、自分達の得意とすることをやろうという暗黙の了解が生まれていたんだ。ザ・キラーズはある特定のタイプの曲を書くバンドだし、僕らはそれを避けるつもりはない。それで「Runaways」が一種の出発点になったんだよ」。
更なる曲がそれに続いた。例えば音楽的な意味で、リード・シングルの"姉妹曲"と言えるアルバム表題曲。また、聴き手の心の琴線に触れる、感情の上での本作の重心「Here With Me」。そして、スタジアムを揺るがすエレクトロ・ロック「Flesh & Bone」など。しかし多くの曲にバンドが納得いくまで磨きがかかる頃には、彼らの候補リストに載っていたプロデューサー達は、誰1人としてアルバム全体に従事することができない状況になっていた。そのため彼らは、ダニエル・ラノワや、スティーヴ・リリーホワイト、ダミアン・テイラー、スチュワート・プライス、そしてブライアン・オブライエンといった、輝かしいプロデューサー陣の面々の出欠可否をチェックしながら、断続的にレコーディングを行うことを余儀なくされたのである。
バンドは当初、そういったプロセスによって、自分達が「ひどく混乱してしまう」かもしれないと不安を抱いていた。だが結局それは、このアルバムに利益をもたらすこと -- そして測り知れないほど貴重ですらあること -- が証明されたのである。これによって彼らは、自分達ならではのサウンドをより鋭く理解できるようになっただけではない。とある1曲 -- 優しいブルーアイド・ソウルの「Heart Of A Girl」-- が、U2やボブ・ディランを手掛けたプロデューサー、ダニエル・ラノワとのスタジオ内コラボレーションから、嬉しい偶然の産物として生まれたのだった。
「あの曲はダニエルと書いたんだ。面白かったよ。というのも僕らは、それまで誰か他の人と何かを書いたことは一度もなかったからね」とロニー。「プロデューサーの中には、"5人目のメンバー"のような立場で取り組んでくれる人もいた。そういう人達は、パッとギターを手にして、バンドと一緒にスタジオに入ってくれたりするんだ。その曲(「Heart Of A Girl」)は、全編ライヴ演奏で録音したんだよ、仕上がるまで1時間しかかからなかった。2テイクほどやって、それでおしまい。やっていて本当に楽しい曲だったね」
最終的には、こういったブツ切りのレコーディング過程を経ることで、ロニー曰く、彼らは「ザ・キラーズにはザ・キラーズらしいやり方が、特定のソングライティング・スタイルがあるんだってことが分かったんだ。今回のアルバムは、通しで5人のプロデューサーとやったわけだけど、それでもやっぱりザ・キラーズらしく聴こえるんだよね……」。
『Battle Born』の真の勝利は、正にその点にある。アルバムと同名のスタジオで全編をレコーディングした本作には、これまでの各作品がそれぞれ持っていた要素が全て組み込まれているのだ。つまり、物語の細部に目を向けた『ホット・ファス』の鋭い視点、『サムズ・タウン』の神話的なアメリカーナ、そして『デイ&エイジ』の問答無用のフックやポップ性がありながら、同時にそのどれか1つにあからさまに偏ったりしてはいない。これは自分達のアイデンティティを受け入れ、それを称えているバンドが生み出したサウンドだ。ブランドンの金言を借りれば、『Battle Born』は、ザ・キラーズが「自分達の最も得意とするところを発揮している」アルバムなのである。
「4人が1つの部屋に集まって、『せーの』で演奏するサウンド。その原点に立ち返る準備が、僕らには出来ていたんだ」と、認めるロニー。「『デイ&エイジ』は素晴らしいアルバムだった。でも僕らは実験することや、曲を作り出すことを楽しみすぎてたんだよね。それが、このバンドに一貫して流れている、共通の"自分達らしさ"を見出す障害になっていた。今回は、『これこそザ・キラーズ』だと自分なりに感じられるような青写真を、自分達自身の手で形にしなくてはいけなかったんだ」
本作が、ライヴ・アリーナとファンの期待とを念頭において作られたアルバムとなっているのは、そのためだ。トム・ペティやデペッシュ・モード、シンプル・マインズらを髣髴とさせる、風にさらされた映画風バラード「Here With Me」は、ライヴの人気曲となること間違いなし。一方、哀調に満ちた「Miss Atomic Bomb」(ラスヴェガスの美人コンテストと、地上核実験がネヴァダ州の観光の目玉だった時代について言及している曲)は、ザ・キラーズの代名詞的ナンバーの1つ「ミスター・ブライトサイド」と期せずして同じDNAを共有しているおかげで、耳聡いリスナーのアンテナに乗ること請け合いである。
ザ・キラーズのデビューから10年間のストーリー -- つまり、ラスヴェガスのホテルのベルボーイから、グラストンベリー・フェスのトリを飾るまでになり、世界最強のライヴ・バンドの1つに数えられ、ブリット、NME、MTVをはじめとする数々の音楽賞に輝き、(そして最も最近では)ASCAP賞を受賞して、彼らの棚はトロフィーや盾がひしめく状態になっている -- は、圧倒的な成功物語である。今回の『Battle Born』は、その物語を構成する最新かつ最高の章だが、しかしロニーはそれでも尚、「アルバムはどれも"実力試しの場"なんだ。僕らは新作を出す度に、要求の水準を上げなくちゃいけないと感じる。現在の栄光に満足することには興味がないんだ」と語って譲らない。
その一方で、ようやく新作リリースの準備が整った今、4人のメンバーは全員、それを引っ提げてツアーに出るのが待ち切れない様子だ。この夏、彼らはアメリカとヨーロッパを周り、ザ・キラーズを世界に"再紹介"することになっている。
「今度のアルバムには、これまで以上にライヴにぴったりの瞬間があると感じるんだ」とブランドン。「これまでと比べて、今回の曲は聴き手により共感してもらえたり、『わかる!』と思ってもらえるんじゃないかと感じてる。今作は僕らにとって、階級の壁を超越した(※ボクシングのたとえ)最強のアルバムだし、すごくワクワクしてるんだ。ありのままの自分達でいることに、僕らは以前より居心地の良さを感じるようになっている。そして、ありのままの自分達を誇りに思っているんだ」
そう語る彼らは、正に「戦いが生んだ州」の真の申し子のようだった。
(レーベルBiographyより)